- 2018年07月27日(金)掲載
- [No.H295] おもちゃ列車・駅・美術館を楽しめる由利高原鉄道[最終回]
- 2018年07月20日(金)掲載
- [No.H294] 拙著「東海鉄道散歩」が7月21日に発刊されます
- 2018年07月13日(金)掲載
- [No.H293] 鉄道日本一(7) 最短営業距離のモノレールと地下鉄
- 2018年07月06日(金)掲載
- [No.H292] 山陰デスティネーションキャンペーンで注目の列車
- 2018年06月29日(金)掲載
- [No.H291] 貨物列車が通せんぼをする踏切…秩父鉄道
- 2018年06月22日(金)掲載
- [No.H290] 鉄道の父「井上勝」像でつながる山陰本線萩駅と東京駅
- 2018年06月15日(金)掲載
- [No.H289] 鉄道の父「井上勝」像がある、山陰本線萩駅
- 2018年06月08日(金)掲載
- [No.H288] 大阪市営地下鉄は、民営化して Osaka Metro に
"鉄道フォーラム"代表の伊藤博康氏による鉄道コラム。
毎回幅広いテーマの中から、「乗ってみたい」「知って良かった」「へぇ~」な汽車旅関連の話題をご紹介します。お楽しみに!
毎回幅広いテーマの中から、「乗ってみたい」「知って良かった」「へぇ~」な汽車旅関連の話題をご紹介します。お楽しみに!
大阪の交通科学博物館が、来年4月6日で営業終了に [No.H069]
国内の鉄道関係博物館といえば、かつて、東京神田の交通博物館と、大阪弁天町の交通科学博物館が東西を代表するものでした。東京の交通博物館は、2007(平成19)年10月に大宮へ移転して鉄道博物館となっています。一方、大阪の交通科学博物館も、2014(平成26)年4月6日(日)を最後に営業を終了し、その2年後となる2016(平成28)年の春に、京都の梅小路蒸気機関車館と同じエリアに京都鉄道博物館として開館する予定となっています。
つまり、弁天町の交通科学博物館に行けるのは、あと3カ月強の期間となります。同館に通った経験のある方、一度行こうと思いながらもまだ行けていない方、そういえばご無沙汰しているなと思う方も多いことと思います。その最後の思い出作りに、改めて出かけてみてはいかがでしょう。
営業終了を控えた交通科学博物館では、いま、さよならイベントを開催中です。年末までのイベントは終了していますが、年明けから閉館までのさよならイベントをご紹介しましょう。
○交通科学博物館さよなら企画展Part II「52年の軌跡展」
1月11日(土)~4月6日(日)
1962(昭和37)年開設から52年にわたり営業してきた交通科学博物館が、どのような展示・活動をしてきたかを紹介するものです。1962年は東海道新幹線開業の2年前で、東海道本線を特急「こだま」が走っていた時代です。それから半世紀強のあいだに、鉄道の社会における位置づけは大きく変わり、国鉄も分割民営化されました。これらの動きと密接に関わってきた交通科学博物館だけに、その内容が期待されるところです。
○保存車両大公開!~こうはく乗り物大公開編~
1月5日(日)~3月30日(日)の各日曜日と、3月21日(祝・金)22日(土)29日(土)
各日、10:30~12:00と13:00~17:00
年明けから、毎日曜日と3月後半には土曜日にも、いつもは非公開の保存車両の車内を公開します。いずれも貴重な車両だけに、この機会にじっくりと見学したいところです。公開予定の車両と期日は、次の通りです。
交通科学博物館へ行く際、弁天町駅の改札階から道路を越えるアーチ型の橋を渡りますが、その際、右の写真の右下にある銘板にも注目しましょう。同銘板には、この跨道橋の名称が「交通科学館架道橋」であることが記されています。交通科学博物館は、開館当時に交通科学館という名称でした。その名残がここにあるわけです。ちなみに、交通科学博物館と名称変更したのは、1990(平成2)年のことでした。
銘板には、設計が天王寺鉄道管理局と住友金属工業であり、昭和38年4月23日に竣工と記されています。交通科学博物館の開業は前述のとおり1962(昭和37)年ですが、これは大阪環状線の開通記念事業の一環でした。その開館の翌年にこの跨線橋が国鉄天王寺鉄道管理局によって架けられていることがわかります。
いわば、交通科学博物館のルーツである国鉄の遺産といえましょう。
なお、交通科学博物館は毎週月曜日がお休みです。月曜日が祝日の場合は翌火曜日の休みとなります。また、年末年始は12月29日~1月2日がお休みですので、ご注意下さい。
PS.
当コラムは、今回が今年最後の記事となります。
本年も、お読み下さりありがとうございました。
新年は、1月10日(金)公開から再開する予定です。
良いお年をお迎え下さい。
掲載日:2013年12月20日
つまり、弁天町の交通科学博物館に行けるのは、あと3カ月強の期間となります。同館に通った経験のある方、一度行こうと思いながらもまだ行けていない方、そういえばご無沙汰しているなと思う方も多いことと思います。その最後の思い出作りに、改めて出かけてみてはいかがでしょう。
営業終了を控えた交通科学博物館では、いま、さよならイベントを開催中です。年末までのイベントは終了していますが、年明けから閉館までのさよならイベントをご紹介しましょう。
○交通科学博物館さよなら企画展Part II「52年の軌跡展」
1月11日(土)~4月6日(日)
1962(昭和37)年開設から52年にわたり営業してきた交通科学博物館が、どのような展示・活動をしてきたかを紹介するものです。1962年は東海道新幹線開業の2年前で、東海道本線を特急「こだま」が走っていた時代です。それから半世紀強のあいだに、鉄道の社会における位置づけは大きく変わり、国鉄も分割民営化されました。これらの動きと密接に関わってきた交通科学博物館だけに、その内容が期待されるところです。
○保存車両大公開!~こうはく乗り物大公開編~
1月5日(日)~3月30日(日)の各日曜日と、3月21日(祝・金)22日(土)29日(土)
各日、10:30~12:00と13:00~17:00
年明けから、毎日曜日と3月後半には土曜日にも、いつもは非公開の保存車両の車内を公開します。いずれも貴重な車両だけに、この機会にじっくりと見学したいところです。公開予定の車両と期日は、次の通りです。
| 1月 (1/5,12,19,26) |
国鉄東名ハイウェイバス1号車 エアロ・コマンダー680F型 |
| 2月 (2/2,9,16,23) |
EF52形電気機関車1号 0系新幹線電車(35形1号、16形1号、21形1号) |
| 3月 (3/2,16,22,29) |
スシ28形301号 マロネフ59形1号 |
| 3月 (3/9,21,23,30) |
80系電車(クハ86形1号) キハ81形ディーゼル動車3号 |
交通科学博物館へ行く際、弁天町駅の改札階から道路を越えるアーチ型の橋を渡りますが、その際、右の写真の右下にある銘板にも注目しましょう。同銘板には、この跨道橋の名称が「交通科学館架道橋」であることが記されています。交通科学博物館は、開館当時に交通科学館という名称でした。その名残がここにあるわけです。ちなみに、交通科学博物館と名称変更したのは、1990(平成2)年のことでした。
銘板には、設計が天王寺鉄道管理局と住友金属工業であり、昭和38年4月23日に竣工と記されています。交通科学博物館の開業は前述のとおり1962(昭和37)年ですが、これは大阪環状線の開通記念事業の一環でした。その開館の翌年にこの跨線橋が国鉄天王寺鉄道管理局によって架けられていることがわかります。
いわば、交通科学博物館のルーツである国鉄の遺産といえましょう。
なお、交通科学博物館は毎週月曜日がお休みです。月曜日が祝日の場合は翌火曜日の休みとなります。また、年末年始は12月29日~1月2日がお休みですので、ご注意下さい。
PS.
当コラムは、今回が今年最後の記事となります。
本年も、お読み下さりありがとうございました。
新年は、1月10日(金)公開から再開する予定です。
良いお年をお迎え下さい。
掲載日:2013年12月20日
●伊藤 博康(いとう ひろやす)
(有)鉄道フォーラム代表。愛知県犬山市生まれ。パソコン通信NIFTY-Serve草創期から鉄道フォーラムに関わり、1992年から運営責任者。(有)鉄道フォーラムを設立後、独自サーバでサービスを継続中。著書に「日本の “珍々”踏切」(東邦出版)「鉄道ファンのためのトレインビューホテル」「鉄道名所の事典」(東京堂出版)がある。現在、中日新聞社「達人に訊け」でもコラムを連載中。
(有)鉄道フォーラム代表。愛知県犬山市生まれ。パソコン通信NIFTY-Serve草創期から鉄道フォーラムに関わり、1992年から運営責任者。(有)鉄道フォーラムを設立後、独自サーバでサービスを継続中。著書に「日本の “珍々”踏切」(東邦出版)「鉄道ファンのためのトレインビューホテル」「鉄道名所の事典」(東京堂出版)がある。現在、中日新聞社「達人に訊け」でもコラムを連載中。
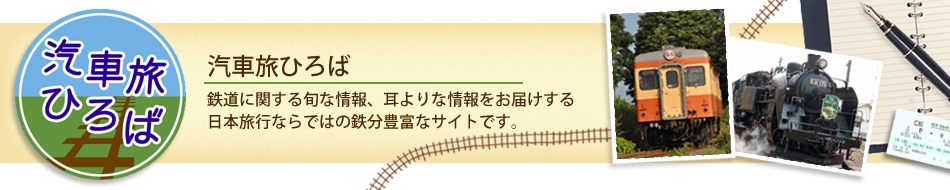







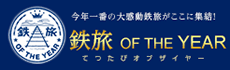




多数の貴重な車両と資料が保存・展示されている。
来る4月6日に営業を終了し、京都梅小路に移転予定だ。