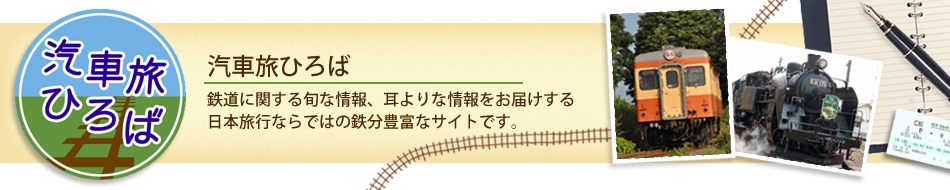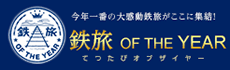- 2018年07月27日(金)掲載
- [No.H295] おもちゃ列車・駅・美術館を楽しめる由利高原鉄道[最終回]
- 2018年07月20日(金)掲載
- [No.H294] 拙著「東海鉄道散歩」が7月21日に発刊されます
- 2018年07月13日(金)掲載
- [No.H293] 鉄道日本一(7) 最短営業距離のモノレールと地下鉄
- 2018年07月06日(金)掲載
- [No.H292] 山陰デスティネーションキャンペーンで注目の列車
- 2018年06月29日(金)掲載
- [No.H291] 貨物列車が通せんぼをする踏切…秩父鉄道
- 2018年06月22日(金)掲載
- [No.H290] 鉄道の父「井上勝」像でつながる山陰本線萩駅と東京駅
- 2018年06月15日(金)掲載
- [No.H289] 鉄道の父「井上勝」像がある、山陰本線萩駅
- 2018年06月08日(金)掲載
- [No.H288] 大阪市営地下鉄は、民営化して Osaka Metro に
"鉄道フォーラム"代表の伊藤博康氏による鉄道コラム。
毎回幅広いテーマの中から、「乗ってみたい」「知って良かった」「へぇ~」な汽車旅関連の話題をご紹介します。お楽しみに!
毎回幅広いテーマの中から、「乗ってみたい」「知って良かった」「へぇ~」な汽車旅関連の話題をご紹介します。お楽しみに!
JR和歌山線にある高野口駅は、高野山詣での拠点だった [No.H179]
高野山へのアクセスは、鉄道だと南海高野線に乗って行くのが当たり前のイメージです。ところが、鉄道がなかった頃には、高野山への道がいくつもありました。そのなかに高野街道があり、奈良に向かう大和街道と交わる地に高野口ができました。いまは橋本市に合併されていますが、それ以前は高野口町だった地です。高野豆腐の原料を多く生産し、いまも高野豆腐を作っている地だそうです。
その高野口駅は、南海高野線との乗換駅となる橋本駅からJR和歌山線で西へ2駅、5. 5kmも離れています。そのうえ、南海電鉄の極楽橋行とは逆方向に進みます。どんどん高野山から離れて行くように感じて不安になりますが、地図を見るとそうではありません。南海高野線は、いったん紀ノ川の上流に向かい、川幅が狭くなったところで渡っています。その後、ほぼ180度方向を変えて下流に向かい、前回紹介した真田幸村蟄居の地・九度山へと進むのです。その橋本~九度山間は7. 5kmです。
ところが、JR和歌山線の高野山口駅から南へ続く道を歩くと、約1. 5kmで紀ノ川右岸に着きます。紀ノ川の川幅は広いものの、そこに架かる九度山橋を渡ると、もう前回紹介した九度山の道の駅がすぐ近くです。ここまでわずか約2キロで、九度山駅まで行っても3キロを切る距離です。南海高野線が如何に大回りをしているかを感じますし、高野口という地名と駅名にも納得できる立地でした。
そんな高野山詣でで賑わった高野口だけに、高野口駅舎もなかなかしっかりとした建物です。時節柄、駅前には六文銭を描いた「九度山」の赤い旗が建てられていました。
高野山駅は無人駅となっていますが、いまもよく整備されていて、駅前にはタクシーも停まっています。その和歌山方面へのホームに、左の写真の柱があります。いまのホーム屋根はその後に造り替えられたものですけど、このオリジナルの柱一本をわざわざ残してあるのです。
その柱の地面に近いところを拡大して、写真右上につけました。「鐵道院」と刻まれていることが判りますよね。鐵道院は、当時の国有鉄道を担当していた政府の部署で、明治41年に設置されています。高野口駅ができたのが明治45年ですから、時代的にも合います。
ちなみに、鉄道院は大正9年に鉄道省となり、戦後に国鉄となっています。この変遷から、首都圏や関西圏の近距離電車の呼び名が、「院電」→「省電」→「国電」と推移しました。しかし、JRになるにあたって決めた「E電」がその後に続くはずでしたが、定着しないまま消えてしまい、いまは該当する言葉がなくなっています。
閑話休題
この柱の反対側には、「明治四十五年」と思われる文字も刻まれていましたが、かなり読みづらくて、最後の二文字ははっきり判りませんでした。
同駅に行ったら、ぜひ見て欲しい柱です。
高野口駅前には、右の写真にある木造三階建ての立派な建物があります。
いまは営業をやめていますが、かつて「葛城館」という旅館だった建物で、明治後期の建築ということですから、まさに高野口駅の開業を前提に建てられたものと思われます。
木造3階建てというだけでも珍しいですが、1階から3階まで正面がすべてガラス張りです。2階と3階はガラス窓のすぐ内側に高欄が設けられ、その2階の高欄には円い穴を開けてあります。高欄の先は短い桟敷を経て障子戸になっているようで、屋根には唐破風があるなど、意匠に工夫を凝らした建物です。
南海高野線の橋本~九度山間は大正13年に開業、極楽橋までの全通は昭和4年のことですから、その全通以前の大正年間に、この葛城館は特に賑わっていたものと思われます。近年は宴会場として使用されていたようですが、営業を終えてからは内部が通常非公開となっているのが残念なところです。それでも、一見の価値があります。
九度山へ行くなら、行きか帰りに、九度山の道の駅からこの高野口駅へと散歩がてらに足を伸ばすのもお勧めです。
掲載日:2016年03月11日
その高野口駅は、南海高野線との乗換駅となる橋本駅からJR和歌山線で西へ2駅、5. 5kmも離れています。そのうえ、南海電鉄の極楽橋行とは逆方向に進みます。どんどん高野山から離れて行くように感じて不安になりますが、地図を見るとそうではありません。南海高野線は、いったん紀ノ川の上流に向かい、川幅が狭くなったところで渡っています。その後、ほぼ180度方向を変えて下流に向かい、前回紹介した真田幸村蟄居の地・九度山へと進むのです。その橋本~九度山間は7. 5kmです。
ところが、JR和歌山線の高野山口駅から南へ続く道を歩くと、約1. 5kmで紀ノ川右岸に着きます。紀ノ川の川幅は広いものの、そこに架かる九度山橋を渡ると、もう前回紹介した九度山の道の駅がすぐ近くです。ここまでわずか約2キロで、九度山駅まで行っても3キロを切る距離です。南海高野線が如何に大回りをしているかを感じますし、高野口という地名と駅名にも納得できる立地でした。
そんな高野山詣でで賑わった高野口だけに、高野口駅舎もなかなかしっかりとした建物です。時節柄、駅前には六文銭を描いた「九度山」の赤い旗が建てられていました。
高野山駅は無人駅となっていますが、いまもよく整備されていて、駅前にはタクシーも停まっています。その和歌山方面へのホームに、左の写真の柱があります。いまのホーム屋根はその後に造り替えられたものですけど、このオリジナルの柱一本をわざわざ残してあるのです。
その柱の地面に近いところを拡大して、写真右上につけました。「鐵道院」と刻まれていることが判りますよね。鐵道院は、当時の国有鉄道を担当していた政府の部署で、明治41年に設置されています。高野口駅ができたのが明治45年ですから、時代的にも合います。
ちなみに、鉄道院は大正9年に鉄道省となり、戦後に国鉄となっています。この変遷から、首都圏や関西圏の近距離電車の呼び名が、「院電」→「省電」→「国電」と推移しました。しかし、JRになるにあたって決めた「E電」がその後に続くはずでしたが、定着しないまま消えてしまい、いまは該当する言葉がなくなっています。
閑話休題
この柱の反対側には、「明治四十五年」と思われる文字も刻まれていましたが、かなり読みづらくて、最後の二文字ははっきり判りませんでした。
同駅に行ったら、ぜひ見て欲しい柱です。
高野口駅前には、右の写真にある木造三階建ての立派な建物があります。
いまは営業をやめていますが、かつて「葛城館」という旅館だった建物で、明治後期の建築ということですから、まさに高野口駅の開業を前提に建てられたものと思われます。
木造3階建てというだけでも珍しいですが、1階から3階まで正面がすべてガラス張りです。2階と3階はガラス窓のすぐ内側に高欄が設けられ、その2階の高欄には円い穴を開けてあります。高欄の先は短い桟敷を経て障子戸になっているようで、屋根には唐破風があるなど、意匠に工夫を凝らした建物です。
南海高野線の橋本~九度山間は大正13年に開業、極楽橋までの全通は昭和4年のことですから、その全通以前の大正年間に、この葛城館は特に賑わっていたものと思われます。近年は宴会場として使用されていたようですが、営業を終えてからは内部が通常非公開となっているのが残念なところです。それでも、一見の価値があります。
九度山へ行くなら、行きか帰りに、九度山の道の駅からこの高野口駅へと散歩がてらに足を伸ばすのもお勧めです。
掲載日:2016年03月11日
●伊藤 博康(いとう ひろやす)
(有)鉄道フォーラム代表。愛知県犬山市生まれ。パソコン通信NIFTY-Serve草創期から鉄道フォーラムに関わり、1992年から運営責任者。(有)鉄道フォーラムを設立後、独自サーバでサービスを継続中。著書に「日本の “珍々”踏切」(東邦出版)「鉄道ファンのためのトレインビューホテル」「鉄道名所の事典」(東京堂出版)がある。現在、中日新聞社「達人に訊け」でもコラムを連載中。
(有)鉄道フォーラム代表。愛知県犬山市生まれ。パソコン通信NIFTY-Serve草創期から鉄道フォーラムに関わり、1992年から運営責任者。(有)鉄道フォーラムを設立後、独自サーバでサービスを継続中。著書に「日本の “珍々”踏切」(東邦出版)「鉄道ファンのためのトレインビューホテル」「鉄道名所の事典」(東京堂出版)がある。現在、中日新聞社「達人に訊け」でもコラムを連載中。