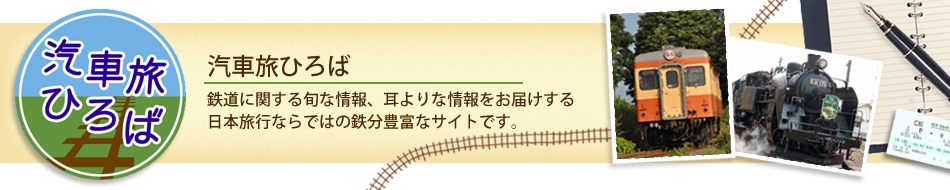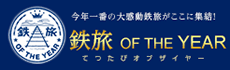- 2018年07月27日(金)掲載
- [No.H295] おもちゃ列車・駅・美術館を楽しめる由利高原鉄道[最終回]
- 2018年07月20日(金)掲載
- [No.H294] 拙著「東海鉄道散歩」が7月21日に発刊されます
- 2018年07月13日(金)掲載
- [No.H293] 鉄道日本一(7) 最短営業距離のモノレールと地下鉄
- 2018年07月06日(金)掲載
- [No.H292] 山陰デスティネーションキャンペーンで注目の列車
- 2018年06月29日(金)掲載
- [No.H291] 貨物列車が通せんぼをする踏切…秩父鉄道
- 2018年06月22日(金)掲載
- [No.H290] 鉄道の父「井上勝」像でつながる山陰本線萩駅と東京駅
- 2018年06月15日(金)掲載
- [No.H289] 鉄道の父「井上勝」像がある、山陰本線萩駅
- 2018年06月08日(金)掲載
- [No.H288] 大阪市営地下鉄は、民営化して Osaka Metro に
"鉄道フォーラム"代表の伊藤博康氏による鉄道コラム。
毎回幅広いテーマの中から、「乗ってみたい」「知って良かった」「へぇ~」な汽車旅関連の話題をご紹介します。お楽しみに!
毎回幅広いテーマの中から、「乗ってみたい」「知って良かった」「へぇ~」な汽車旅関連の話題をご紹介します。お楽しみに!
足尾の鉄道の歴史をさらに楽しむ [No.H192]
前回、足尾歴史館を紹介しました。
せっかく足尾まで行くなら、銅山時代に活躍した鉄道についても見たいですよね。
その際、まず見ておきたいのはわたらせ渓谷鐵道の足尾駅です。足尾歴史館最寄りの通洞駅と足尾駅の駅間はわずか900mですから、列車を待つより歩いた方が早いでしょう。
その足尾駅には、NPO法人足尾歴史館が管理する「足尾駅の保存車両」があります。といっても、博物館等としての建物があるわけではありません。同NPO法人が保存している機関車・貨車移動機・貨車・気動車等が保存されているのです。
ただし、年に3回行われる一般公開日を除くと、多くの車両はシートにくるまれたままの状態です。そのなかで、外観だけながらいつでも見られるのが、右の写真にある気動車キハ35-70とキハ30-35です。
この気動車2両が停まっているのはもと貨物ホームで、そのプラットホームと上屋は、国の登録有形文化財になっています。
同じく、写真の右上にある足尾駅舎も登録有形文化財になっているほか、上下プラットホームとレンガ造りの危険品庫も登録有形文化財になっています。
列車を待つ間、これらの登録有形文化財を眺めてすごいのも良いものです。
余談ながら、昨年(2015年)に話題となった映画「海街diary」のロケに、この足尾駅が使われました。映画のロケ地になるほど、雰囲気の良い駅です。
足尾駅と終点の間藤駅の駅間は、1. 3kmです。これまた歩ける距離ですが、そのほぼ中間付近でわたらせ渓谷鐵道は松木川を渡ります。この第一松木川橋梁が、なかなか渋い佇まいを見せてくれます。
左の写真がその第一松木川橋梁です。石積みの橋脚の上に、鋼材を組み合わせた小さな橋脚が載っているという、珍しい構造をしています。
小さな鋼材を組み合わせた橋脚は「トレッスル橋」と呼ばれ、これだけでも珍しい存在です。当コラムでは、これまでに、次のトレッスル橋を取りあげています。
南海高野線のトレッスル橋「中古沢橋梁」へ行く [No.H138]
鉄道文化財をめぐる(6) 余部鉄橋「空の駅」 [No.H050]
これらはいずれも大規模なトレッスル橋です。それらに比べて、この第一松木川橋梁はいかに小規模かが判るでしょう。大正3(1914)年に架橋されていますので、すでに100年を超えた歴史ある鉄橋です。
写真ではパッと見で橋脚が一つだけに見えますが、よく見ると左端にもトレッスル橋脚が写っています。歩道とほぼ接するような状態です。
この2つのトレッスル橋脚で、3つのプレートガーダーの桁を支えて松木川を越す構造です。
同橋の奥にも古そうな鉄橋が見えますが、こちらは旧県道で、いまも人道橋として渡ることができますので、第一松木川橋梁を真横からも観察することができます。
ちなみに、この第一松木川橋梁も国の登録有形文化財です。また、松木川はこのすぐ下流で神子内川と合流して、渡良瀬川となります。
わたらせ渓谷鐵道は、盲腸線と呼ばれる行き止まり式の線形です。
その終点・間藤(まとう)駅に立つと、線路はその先まで伸びていることに気付きます。
どこまで敷かれているのか気になりますが、1. 9km先の足尾本山(ほんざん)駅まで続いています。
この間藤~足尾本山間も、先の第一松木橋梁と同じ大正3年に開通しました。
国鉄時代に貨物営業を止めているのですが、国鉄分割民営化時になぜか廃止とならず、JR東日本に引き継がれています。ただし、第三セクター鉄道としてわたらせ渓谷鐵道ができると同時に、廃止となっています。
その線路はいまもほぼ廃止時のままとなっていて、所々で見られる廃線跡は、その廃止後の年月を感じさせる状態です。
ただし、間藤駅から約500mのところにあった県道との踏切については、踏切道が舗装されたことで、線路が分断されています。とはいえ、警報機も踏切防護柵もそのまま残っていますので、なんとも不思議な光景となっています。
廃線跡探訪がお好きな方は、間藤駅の先も探索されると楽しめますよ。
掲載日:2016年06月17日
せっかく足尾まで行くなら、銅山時代に活躍した鉄道についても見たいですよね。
その際、まず見ておきたいのはわたらせ渓谷鐵道の足尾駅です。足尾歴史館最寄りの通洞駅と足尾駅の駅間はわずか900mですから、列車を待つより歩いた方が早いでしょう。
その足尾駅には、NPO法人足尾歴史館が管理する「足尾駅の保存車両」があります。といっても、博物館等としての建物があるわけではありません。同NPO法人が保存している機関車・貨車移動機・貨車・気動車等が保存されているのです。
ただし、年に3回行われる一般公開日を除くと、多くの車両はシートにくるまれたままの状態です。そのなかで、外観だけながらいつでも見られるのが、右の写真にある気動車キハ35-70とキハ30-35です。
この気動車2両が停まっているのはもと貨物ホームで、そのプラットホームと上屋は、国の登録有形文化財になっています。
同じく、写真の右上にある足尾駅舎も登録有形文化財になっているほか、上下プラットホームとレンガ造りの危険品庫も登録有形文化財になっています。
列車を待つ間、これらの登録有形文化財を眺めてすごいのも良いものです。
余談ながら、昨年(2015年)に話題となった映画「海街diary」のロケに、この足尾駅が使われました。映画のロケ地になるほど、雰囲気の良い駅です。
足尾駅と終点の間藤駅の駅間は、1. 3kmです。これまた歩ける距離ですが、そのほぼ中間付近でわたらせ渓谷鐵道は松木川を渡ります。この第一松木川橋梁が、なかなか渋い佇まいを見せてくれます。
左の写真がその第一松木川橋梁です。石積みの橋脚の上に、鋼材を組み合わせた小さな橋脚が載っているという、珍しい構造をしています。
小さな鋼材を組み合わせた橋脚は「トレッスル橋」と呼ばれ、これだけでも珍しい存在です。当コラムでは、これまでに、次のトレッスル橋を取りあげています。
南海高野線のトレッスル橋「中古沢橋梁」へ行く [No.H138]
鉄道文化財をめぐる(6) 余部鉄橋「空の駅」 [No.H050]
これらはいずれも大規模なトレッスル橋です。それらに比べて、この第一松木川橋梁はいかに小規模かが判るでしょう。大正3(1914)年に架橋されていますので、すでに100年を超えた歴史ある鉄橋です。
写真ではパッと見で橋脚が一つだけに見えますが、よく見ると左端にもトレッスル橋脚が写っています。歩道とほぼ接するような状態です。
この2つのトレッスル橋脚で、3つのプレートガーダーの桁を支えて松木川を越す構造です。
同橋の奥にも古そうな鉄橋が見えますが、こちらは旧県道で、いまも人道橋として渡ることができますので、第一松木川橋梁を真横からも観察することができます。
ちなみに、この第一松木川橋梁も国の登録有形文化財です。また、松木川はこのすぐ下流で神子内川と合流して、渡良瀬川となります。
わたらせ渓谷鐵道は、盲腸線と呼ばれる行き止まり式の線形です。
その終点・間藤(まとう)駅に立つと、線路はその先まで伸びていることに気付きます。
どこまで敷かれているのか気になりますが、1. 9km先の足尾本山(ほんざん)駅まで続いています。
この間藤~足尾本山間も、先の第一松木橋梁と同じ大正3年に開通しました。
国鉄時代に貨物営業を止めているのですが、国鉄分割民営化時になぜか廃止とならず、JR東日本に引き継がれています。ただし、第三セクター鉄道としてわたらせ渓谷鐵道ができると同時に、廃止となっています。
その線路はいまもほぼ廃止時のままとなっていて、所々で見られる廃線跡は、その廃止後の年月を感じさせる状態です。
ただし、間藤駅から約500mのところにあった県道との踏切については、踏切道が舗装されたことで、線路が分断されています。とはいえ、警報機も踏切防護柵もそのまま残っていますので、なんとも不思議な光景となっています。
廃線跡探訪がお好きな方は、間藤駅の先も探索されると楽しめますよ。
掲載日:2016年06月17日
●伊藤 博康(いとう ひろやす)
(有)鉄道フォーラム代表。愛知県犬山市生まれ。パソコン通信NIFTY-Serve草創期から鉄道フォーラムに関わり、1992年から運営責任者。(有)鉄道フォーラムを設立後、独自サーバでサービスを継続中。著書に「日本の “珍々”踏切」(東邦出版)「鉄道ファンのためのトレインビューホテル」「鉄道名所の事典」(東京堂出版)がある。現在、中日新聞社「達人に訊け」でもコラムを連載中。
(有)鉄道フォーラム代表。愛知県犬山市生まれ。パソコン通信NIFTY-Serve草創期から鉄道フォーラムに関わり、1992年から運営責任者。(有)鉄道フォーラムを設立後、独自サーバでサービスを継続中。著書に「日本の “珍々”踏切」(東邦出版)「鉄道ファンのためのトレインビューホテル」「鉄道名所の事典」(東京堂出版)がある。現在、中日新聞社「達人に訊け」でもコラムを連載中。