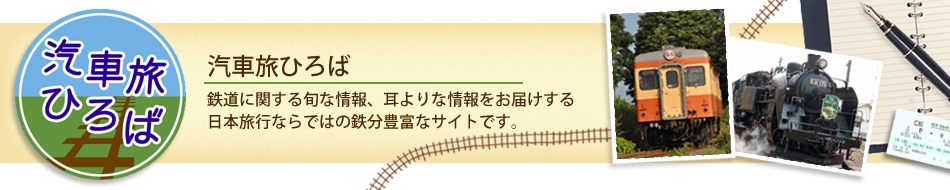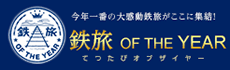- 2018年07月27日(金)掲載
- [No.H295] おもちゃ列車・駅・美術館を楽しめる由利高原鉄道[最終回]
- 2018年07月20日(金)掲載
- [No.H294] 拙著「東海鉄道散歩」が7月21日に発刊されます
- 2018年07月13日(金)掲載
- [No.H293] 鉄道日本一(7) 最短営業距離のモノレールと地下鉄
- 2018年07月06日(金)掲載
- [No.H292] 山陰デスティネーションキャンペーンで注目の列車
- 2018年06月29日(金)掲載
- [No.H291] 貨物列車が通せんぼをする踏切…秩父鉄道
- 2018年06月22日(金)掲載
- [No.H290] 鉄道の父「井上勝」像でつながる山陰本線萩駅と東京駅
- 2018年06月15日(金)掲載
- [No.H289] 鉄道の父「井上勝」像がある、山陰本線萩駅
- 2018年06月08日(金)掲載
- [No.H288] 大阪市営地下鉄は、民営化して Osaka Metro に
"鉄道フォーラム"代表の伊藤博康氏による鉄道コラム。
毎回幅広いテーマの中から、「乗ってみたい」「知って良かった」「へぇ~」な汽車旅関連の話題をご紹介します。お楽しみに!
毎回幅広いテーマの中から、「乗ってみたい」「知って良かった」「へぇ~」な汽車旅関連の話題をご紹介します。お楽しみに!
青函トンネル入口広場にトンネル神社ができた [No.H207]
青函トンネルは、本州と北海道を結ぶ53. 85kmの鉄道用海底トンネルとして、1988(昭和63)年3月13日から使われています。今年(2016年)3月26日には、青函トンネルを使って北海道新幹線の新青森~新函館北斗間148. 8kmが開業しました。そのうちの3分の1以上が青函トンネルということになります。
その青函トンネルの本州側入口付近には、地元今別町が「青函トンネル入口広場」を整備し、無料開放してきました。その広場に今春、北海道新幹線開業を記念して「トンネル神社」が建立されました。ご神体は「叶明神」として、本坑貫通時に出た石を祀ってあります。難工事にも負けずに貫通が叶った青函トンネルにあやかったものということです。
その祠に向かって右側にも「貫通石」が設置してあります。こちらは、地元の方が保存されていたもののようで、ボーリング跡なのか、丸い穴が空いています。
神社の左後方には、青函トンネルの本州側入口が見えています。
「青函トンネル入口広場」は、北海道新幹線の東側に駐車場、西側に見学用の広場を設けた施設です。その東西は、線路の下を通る道路で結ばれています。
トンネル神社は、その東側にある駐車場の一角にあります。同じ駐車場内の線路際には、左の写真に写っている公衆トイレもあります。近くには、コンビニをはじめ用を足せる場所がないだけに、ありがたい施設です。
その公衆トイレは、北海道新幹線を走るE5系やH5系の車体色となっています。窓下の帯がグレーなのでどちらの塗装かは確定できないのですが、両車両が走るところなので、敢えてグレーにしたのでしょうか。ちなみに、帯の色がピンク色であればJR東日本のE5系、彩香(さいか)パープルであればJR北海道のH5系となります。
公衆トイレの奥に白っぽい防音壁がありますが、その防音壁の先が線路です。その防煙壁の右上に顔を出している茶色いものは、西側の広場に今春できた展望台です。
では、西側の広場に行ってみましょう。
線路をくぐる道路から、階段を少し登ったところになります。
整備されていて、線路に面した部分には柵や垣根があります。線路から適度な距離をとってあるので、安全に見学ができるようになっているのです。
右の写真は、前述の展望台から撮っていますが、多くの方は、ご覧のように線路際に集まって新幹線を待ちます。その新幹線の通過予想時刻は、広場に掲示されていますし、今別町が作る奥津軽いまべつ駅開業ホームページでも、「ニュース」ページの3月30日付に記してあります。ただし、あくまで予想であること、それに貨物列車も通過するため、この予想時刻がすべてではないということは留意しておきたいところです。
なお、列車が近付くと警報音が鳴りますので、知らない間に通過してしまったということはありません。ご安心下さい。
ところで、この青函トンネル入口広場の場所ですが、いささか不便なところになります。
津軽半島を車でまわり、竜飛崎に行くとか、青函トンネル記念館に行くという方でしたら良いのですが、鉄道で行くとなると、津軽線の終点となる三厩(みんまや)駅か、その一つ手前の津軽浜名駅が最寄りとなります。三厩駅からは約2. 5km、津軽浜名駅からだと2km弱で、やや津軽浜名駅の方が近くなります。ただし、道のりは三厩駅からの方がやや判りやすいかなという感じです。
いずれにしても、沿道にお店などはほとんどないので、飲食物は事前に確保していく必要があります。また、海霧が発生するところで、暑いと思っていたらいきなり霧に覆われて意外なほど冷えたりします。もともと本州最北端の寒冷な地だけに、体温調整ができる服装が求められます。
その分、空気が新鮮で気持ちの良いところです。
この方面に行くなら、地図を片手にちょっと立ち寄ってみたいところです。
掲載日:2016年09月30日
その青函トンネルの本州側入口付近には、地元今別町が「青函トンネル入口広場」を整備し、無料開放してきました。その広場に今春、北海道新幹線開業を記念して「トンネル神社」が建立されました。ご神体は「叶明神」として、本坑貫通時に出た石を祀ってあります。難工事にも負けずに貫通が叶った青函トンネルにあやかったものということです。
その祠に向かって右側にも「貫通石」が設置してあります。こちらは、地元の方が保存されていたもののようで、ボーリング跡なのか、丸い穴が空いています。
神社の左後方には、青函トンネルの本州側入口が見えています。
「青函トンネル入口広場」は、北海道新幹線の東側に駐車場、西側に見学用の広場を設けた施設です。その東西は、線路の下を通る道路で結ばれています。
トンネル神社は、その東側にある駐車場の一角にあります。同じ駐車場内の線路際には、左の写真に写っている公衆トイレもあります。近くには、コンビニをはじめ用を足せる場所がないだけに、ありがたい施設です。
その公衆トイレは、北海道新幹線を走るE5系やH5系の車体色となっています。窓下の帯がグレーなのでどちらの塗装かは確定できないのですが、両車両が走るところなので、敢えてグレーにしたのでしょうか。ちなみに、帯の色がピンク色であればJR東日本のE5系、彩香(さいか)パープルであればJR北海道のH5系となります。
公衆トイレの奥に白っぽい防音壁がありますが、その防音壁の先が線路です。その防煙壁の右上に顔を出している茶色いものは、西側の広場に今春できた展望台です。
では、西側の広場に行ってみましょう。
線路をくぐる道路から、階段を少し登ったところになります。
整備されていて、線路に面した部分には柵や垣根があります。線路から適度な距離をとってあるので、安全に見学ができるようになっているのです。
右の写真は、前述の展望台から撮っていますが、多くの方は、ご覧のように線路際に集まって新幹線を待ちます。その新幹線の通過予想時刻は、広場に掲示されていますし、今別町が作る奥津軽いまべつ駅開業ホームページでも、「ニュース」ページの3月30日付に記してあります。ただし、あくまで予想であること、それに貨物列車も通過するため、この予想時刻がすべてではないということは留意しておきたいところです。
なお、列車が近付くと警報音が鳴りますので、知らない間に通過してしまったということはありません。ご安心下さい。
ところで、この青函トンネル入口広場の場所ですが、いささか不便なところになります。
津軽半島を車でまわり、竜飛崎に行くとか、青函トンネル記念館に行くという方でしたら良いのですが、鉄道で行くとなると、津軽線の終点となる三厩(みんまや)駅か、その一つ手前の津軽浜名駅が最寄りとなります。三厩駅からは約2. 5km、津軽浜名駅からだと2km弱で、やや津軽浜名駅の方が近くなります。ただし、道のりは三厩駅からの方がやや判りやすいかなという感じです。
いずれにしても、沿道にお店などはほとんどないので、飲食物は事前に確保していく必要があります。また、海霧が発生するところで、暑いと思っていたらいきなり霧に覆われて意外なほど冷えたりします。もともと本州最北端の寒冷な地だけに、体温調整ができる服装が求められます。
その分、空気が新鮮で気持ちの良いところです。
この方面に行くなら、地図を片手にちょっと立ち寄ってみたいところです。
掲載日:2016年09月30日
●伊藤 博康(いとう ひろやす)
(有)鉄道フォーラム代表。愛知県犬山市生まれ。パソコン通信NIFTY-Serve草創期から鉄道フォーラムに関わり、1992年から運営責任者。(有)鉄道フォーラムを設立後、独自サーバでサービスを継続中。著書に「日本の “珍々”踏切」(東邦出版)「鉄道ファンのためのトレインビューホテル」「鉄道名所の事典」(東京堂出版)がある。現在、中日新聞社「達人に訊け」でもコラムを連載中。
(有)鉄道フォーラム代表。愛知県犬山市生まれ。パソコン通信NIFTY-Serve草創期から鉄道フォーラムに関わり、1992年から運営責任者。(有)鉄道フォーラムを設立後、独自サーバでサービスを継続中。著書に「日本の “珍々”踏切」(東邦出版)「鉄道ファンのためのトレインビューホテル」「鉄道名所の事典」(東京堂出版)がある。現在、中日新聞社「達人に訊け」でもコラムを連載中。