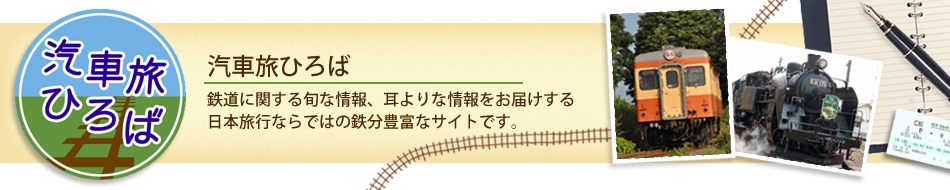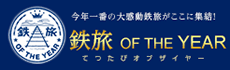- 2018年07月27日(金)掲載
- [No.H295] おもちゃ列車・駅・美術館を楽しめる由利高原鉄道[最終回]
- 2018年07月20日(金)掲載
- [No.H294] 拙著「東海鉄道散歩」が7月21日に発刊されます
- 2018年07月13日(金)掲載
- [No.H293] 鉄道日本一(7) 最短営業距離のモノレールと地下鉄
- 2018年07月06日(金)掲載
- [No.H292] 山陰デスティネーションキャンペーンで注目の列車
- 2018年06月29日(金)掲載
- [No.H291] 貨物列車が通せんぼをする踏切…秩父鉄道
- 2018年06月22日(金)掲載
- [No.H290] 鉄道の父「井上勝」像でつながる山陰本線萩駅と東京駅
- 2018年06月15日(金)掲載
- [No.H289] 鉄道の父「井上勝」像がある、山陰本線萩駅
- 2018年06月08日(金)掲載
- [No.H288] 大阪市営地下鉄は、民営化して Osaka Metro に
"鉄道フォーラム"代表の伊藤博康氏による鉄道コラム。
毎回幅広いテーマの中から、「乗ってみたい」「知って良かった」「へぇ~」な汽車旅関連の話題をご紹介します。お楽しみに!
毎回幅広いテーマの中から、「乗ってみたい」「知って良かった」「へぇ~」な汽車旅関連の話題をご紹介します。お楽しみに!
今秋、一般開放された廃線跡を歩く…武庫川渓谷 [No.H215]
兵庫県の西宮市と宝塚市の市境を流れる武庫川…と記すと、この一帯に土地勘のある方でないと、???となろうかと思います。でも、宝塚といえば、大阪の北西とおおよそ見当がつく方も多いと思います。
その宝塚駅からJR福知山線で一駅北となる生瀬(なまぜ)駅から二駅先の武田尾駅まで、いまはほぼトンネルで抜けています。しかし、国鉄時代の1986年に複線電化されるまでは、武庫川渓谷と呼ばれる武庫川沿いの景勝地を走る路線でした。当時、中間の西宮名塩駅はありませんでした。
廃線後、この廃線跡が人気のハイキングコースとなったのですが、その大半を占める西宮市側は、公式には立ち入り禁止としていました。しかし、新緑や紅葉がきれいな景勝地を通っているうえ、鉄道線路の跡だけに坂は緩やかで人気が衰えません。
そこで、西宮市は土地所有者であるJR西日本と協議して、今年のゴールデンウィーク明けの5月16日から安全対策工事に着手しました。その結果、11月15日に一般開放されたのです。
筆者は、一般開放3日目となる11月17日に、この廃線跡を歩いてきたので、ここに紹介します。
右上の写真に写る鉄橋は、一般開放以前には橋げたの外につけられた保線用通路を歩いていたそうです。それが、ご覧の通り鉄橋内に歩道と手すりが設けられて、安全に渡ることができるようになりました。橋の下は武庫川で、その左岸が宝塚市、右岸が西宮市となっています。つまり、この橋を境にして、廃線跡は生瀬駅側が西宮市、武田尾駅側が宝塚市となっているわけです。
廃線跡の整備というと、路面が整地されていることが多いのですが、ここの多くは枕木がそのまま残っています。レールが撤去されているとはいえ、枕木の上は歩きにくく、ハイカーのほとんどは枕木の左右どちらかを歩いています。
途中で、キロポストを2箇所確認しました。一方は木製で、もう一方はコンクリート製ですが、後者は位置を示す数字が消えていました。
カーブ区間の手前で、半径300メートルで制限時速60キロを示す速度標もありましたが、さび付いていて、かろうじて読める状態です。
渓谷に沿っている区間なので、川側・山側ともに石積みなどの擁壁があり、その保守のための階段が残っている箇所もありました。保線関係の方が待避できるように、川側に張りだした構造物もありました。
このように、鉄道の廃線跡を感じさせるものはいろいろとあります。しかし、それらに関する案内板などは一切なく、あるのは落石注意とか、事故が起きても責任は負わないとする注意書きばかりです。これは、今回、一般公開されるまでの経緯からして、致し方ないものでしょう。
途中、大小多くのトンネルがありますが、内部に一切の照明がありません。なかにはカーブしているトンネルや、長いトンネルがあり、中ほどはまさに真っ暗でなにも見えなくなります。そのような箇所の多くは枕木を撤去してあるなど足元は安全ながら、側壁すら判らなくなるので、懐中電灯などの照明用具の持参が必要です。
その分、トンネル内は現役時代の様子がよく残っていて、右の写真のように、保線関係の方が待避するための横穴が見られるトンネルもありました。
トンネルの多くは下部が石積みで、上部のアーチ部分がレンガ巻きになっています。ただし、コンクリートで補強したり、入口部分をコンクリート製にしていたりと、手を加えていることも判ります。
このように、興味深く廃線跡を楽しみ、渓谷美を楽しみながら歩くことができるハイキングコースでした。
生瀬駅、武田尾駅のどちらから歩いても良いですが、生瀬駅からの場合、最初の1キロ強は国道の歩道を歩くことになります。その代わり、廃線跡を歩き終えたところがほぼ武田尾駅ですので、気持ちよく歩き終えることができます。武田尾駅の近くには武田尾温泉がありますので、やや値が張りますが、温泉で汗を流してから電車に乗ることもできます。
一方、武田尾駅からの場合は、駅からすぐに廃線跡がはじまり、700メートルほどでハイキングコースとなるので、歩きはじめが快適です。全行程が緩やかながら下り坂というメリットもあります。
なお、ハイキングコースは約4.7キロで、前後の一般道部分も含めると約6キロとなります。所要は約2時間、ゆっくり休みながら歩いて3時間といったところです。
照明用具が必要となるなど、自己責任が基本となるところですが、常識的なハイキング装備で十分安全に歩ける区間です。気候の良い時期に出かけてみてはいかがでしょうか?
掲載日:2016年11月25日
その宝塚駅からJR福知山線で一駅北となる生瀬(なまぜ)駅から二駅先の武田尾駅まで、いまはほぼトンネルで抜けています。しかし、国鉄時代の1986年に複線電化されるまでは、武庫川渓谷と呼ばれる武庫川沿いの景勝地を走る路線でした。当時、中間の西宮名塩駅はありませんでした。
廃線後、この廃線跡が人気のハイキングコースとなったのですが、その大半を占める西宮市側は、公式には立ち入り禁止としていました。しかし、新緑や紅葉がきれいな景勝地を通っているうえ、鉄道線路の跡だけに坂は緩やかで人気が衰えません。
そこで、西宮市は土地所有者であるJR西日本と協議して、今年のゴールデンウィーク明けの5月16日から安全対策工事に着手しました。その結果、11月15日に一般開放されたのです。
筆者は、一般開放3日目となる11月17日に、この廃線跡を歩いてきたので、ここに紹介します。
右上の写真に写る鉄橋は、一般開放以前には橋げたの外につけられた保線用通路を歩いていたそうです。それが、ご覧の通り鉄橋内に歩道と手すりが設けられて、安全に渡ることができるようになりました。橋の下は武庫川で、その左岸が宝塚市、右岸が西宮市となっています。つまり、この橋を境にして、廃線跡は生瀬駅側が西宮市、武田尾駅側が宝塚市となっているわけです。
廃線跡の整備というと、路面が整地されていることが多いのですが、ここの多くは枕木がそのまま残っています。レールが撤去されているとはいえ、枕木の上は歩きにくく、ハイカーのほとんどは枕木の左右どちらかを歩いています。
途中で、キロポストを2箇所確認しました。一方は木製で、もう一方はコンクリート製ですが、後者は位置を示す数字が消えていました。
カーブ区間の手前で、半径300メートルで制限時速60キロを示す速度標もありましたが、さび付いていて、かろうじて読める状態です。
渓谷に沿っている区間なので、川側・山側ともに石積みなどの擁壁があり、その保守のための階段が残っている箇所もありました。保線関係の方が待避できるように、川側に張りだした構造物もありました。
このように、鉄道の廃線跡を感じさせるものはいろいろとあります。しかし、それらに関する案内板などは一切なく、あるのは落石注意とか、事故が起きても責任は負わないとする注意書きばかりです。これは、今回、一般公開されるまでの経緯からして、致し方ないものでしょう。
途中、大小多くのトンネルがありますが、内部に一切の照明がありません。なかにはカーブしているトンネルや、長いトンネルがあり、中ほどはまさに真っ暗でなにも見えなくなります。そのような箇所の多くは枕木を撤去してあるなど足元は安全ながら、側壁すら判らなくなるので、懐中電灯などの照明用具の持参が必要です。
その分、トンネル内は現役時代の様子がよく残っていて、右の写真のように、保線関係の方が待避するための横穴が見られるトンネルもありました。
トンネルの多くは下部が石積みで、上部のアーチ部分がレンガ巻きになっています。ただし、コンクリートで補強したり、入口部分をコンクリート製にしていたりと、手を加えていることも判ります。
このように、興味深く廃線跡を楽しみ、渓谷美を楽しみながら歩くことができるハイキングコースでした。
生瀬駅、武田尾駅のどちらから歩いても良いですが、生瀬駅からの場合、最初の1キロ強は国道の歩道を歩くことになります。その代わり、廃線跡を歩き終えたところがほぼ武田尾駅ですので、気持ちよく歩き終えることができます。武田尾駅の近くには武田尾温泉がありますので、やや値が張りますが、温泉で汗を流してから電車に乗ることもできます。
一方、武田尾駅からの場合は、駅からすぐに廃線跡がはじまり、700メートルほどでハイキングコースとなるので、歩きはじめが快適です。全行程が緩やかながら下り坂というメリットもあります。
なお、ハイキングコースは約4.7キロで、前後の一般道部分も含めると約6キロとなります。所要は約2時間、ゆっくり休みながら歩いて3時間といったところです。
照明用具が必要となるなど、自己責任が基本となるところですが、常識的なハイキング装備で十分安全に歩ける区間です。気候の良い時期に出かけてみてはいかがでしょうか?
掲載日:2016年11月25日
●伊藤 博康(いとう ひろやす)
(有)鉄道フォーラム代表。愛知県犬山市生まれ。パソコン通信NIFTY-Serve草創期から鉄道フォーラムに関わり、1992年から運営責任者。(有)鉄道フォーラムを設立後、独自サーバでサービスを継続中。著書に「日本の “珍々”踏切」(東邦出版)「鉄道ファンのためのトレインビューホテル」「鉄道名所の事典」(東京堂出版)がある。現在、中日新聞社「達人に訊け」でもコラムを連載中。
(有)鉄道フォーラム代表。愛知県犬山市生まれ。パソコン通信NIFTY-Serve草創期から鉄道フォーラムに関わり、1992年から運営責任者。(有)鉄道フォーラムを設立後、独自サーバでサービスを継続中。著書に「日本の “珍々”踏切」(東邦出版)「鉄道ファンのためのトレインビューホテル」「鉄道名所の事典」(東京堂出版)がある。現在、中日新聞社「達人に訊け」でもコラムを連載中。