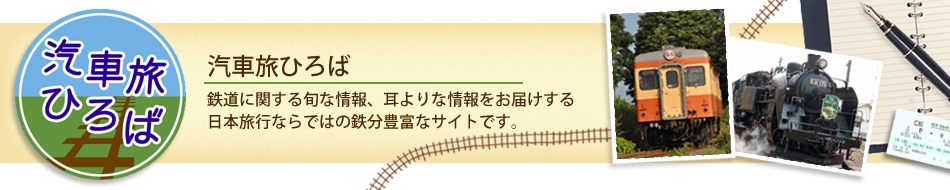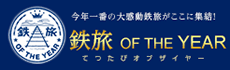- 2018年07月27日(金)掲載
- [No.H295] おもちゃ列車・駅・美術館を楽しめる由利高原鉄道[最終回]
- 2018年07月20日(金)掲載
- [No.H294] 拙著「東海鉄道散歩」が7月21日に発刊されます
- 2018年07月13日(金)掲載
- [No.H293] 鉄道日本一(7) 最短営業距離のモノレールと地下鉄
- 2018年07月06日(金)掲載
- [No.H292] 山陰デスティネーションキャンペーンで注目の列車
- 2018年06月29日(金)掲載
- [No.H291] 貨物列車が通せんぼをする踏切…秩父鉄道
- 2018年06月22日(金)掲載
- [No.H290] 鉄道の父「井上勝」像でつながる山陰本線萩駅と東京駅
- 2018年06月15日(金)掲載
- [No.H289] 鉄道の父「井上勝」像がある、山陰本線萩駅
- 2018年06月08日(金)掲載
- [No.H288] 大阪市営地下鉄は、民営化して Osaka Metro に
"鉄道フォーラム"代表の伊藤博康氏による鉄道コラム。
毎回幅広いテーマの中から、「乗ってみたい」「知って良かった」「へぇ~」な汽車旅関連の話題をご紹介します。お楽しみに!
毎回幅広いテーマの中から、「乗ってみたい」「知って良かった」「へぇ~」な汽車旅関連の話題をご紹介します。お楽しみに!
非電化線を走る電車がJR九州にも登場 [No.H216]
当コラム2014年4月4日付で、非電化線を走る電車“ACCUM”がダイヤ改正で登場を記しました。JR東日本が開発した、蓄電池で走る電車です。
同じ発想の電車をJR九州が開発し、先月となる10月19日から営業運転を始めました。基本的な考え方は同じですが、JR東日本が直流1500Vで充電するのに対して、JR九州は交流20000Vで充電しています。JR東日本は首都圏を中心に直流区間が多いのに対して、JR九州は関門海峡を除いた全線が交流電化となっているためです。
また、モーターに近年普及を始めた永久磁石を使用した、永久磁石同期電動機を使用している点でも進歩しています。
車両の外観は、ご覧の通りJR九州らしいものですが、イメージカラーとして明るい青色を使っているところに特色があり、他の車両と見た目で容易に区別が付きます。
2両編成ですが、下り方の車両の床下に蓄電池を積んでいます。その部分はイメージカラーの青い覆いで覆われているので、遠目にもそれと判ります。一方、上り方の車両にはパンタグラフがあり、モーターもこちらの車両にあります。
車両形式は819系ですが、形式名はクモハBEC819-クハBEC818という、アルファベットの入った珍しいものとなりました。BECは、Battery Electric Car の略のようです。また、JR東日本の「ACCUM」と同じく愛称がつきました。「DENCHA」という愛称で、「Dual ENergy CHArge TRAIN」から名づけたということです。
隣接車両との扉近くの壁にはモニターが設置されていて、左画像のとおり、その時の電気の使用状況をリアルタイムで表示しています。この画面は、本城駅に停まるためにブレーキをかけた状態で、モーターで発生した電気を制御装置を経て蓄電池に溜めている様子を表しています。これも、JR東日本の「ACCUM」車内で見られるものと同様です。
いま、819系DENCHAが営業運転しているのは、筑豊本線の折尾~若松間10. 8kmです。筑豊地区の炭鉱が盛況だった頃に、その石炭の積み出し港として栄えた若松につながる線路だけに、非電化でありながら複線となっています。
その後の電化の進展で、鹿児島本線からの直通列車が走るようになった折尾以南は電化されたのに対して、折尾~若松間は非電化のままという支線的な扱いとなっています。その区間でJR九州初の蓄電池電車719系DENCHAの試験運転をして、さらに営業運転もはじめたという次第です。
819系DENCHAは、今のところ火曜日を除く毎日、11時過ぎから折尾~若松間を2往復し、その後車両センターのある直方までパンタグラフを上げて蓄電しながら回送で一往復します。さらに、14時過ぎからまた折尾~若松間を2往復する運用となっています。
その様子を見たところ、折尾駅停車中にパンタグラフを降ろして非電化区間での運転をはじめ、2往復を終えると折尾駅でパンタグラフを上げて、蓄電しながら直方へ向かうという対応をしていました。
車内は予想以上に静かで驚きました。VVVFインバーター制御が登場した頃は、これでもかというほど大きな音がしていたものですが、それも技術の進歩で低騒音化されているようです。
営業運転開始から1ヶ月以上経ちますが、これまでに特にトラブルの情報は無いようで、順調に走っている様子です。さらに来春には量産車6編成12両が登場して、筑豊本線で本格的な運行を開始する見込みです。筑豊本線は平坦な路線ですので、蓄電池電車の初期性能の検証には適しているのでしょう。
JR九州としてはこの先、老朽化したディーゼルカーの代替車としてDENCHAを投入していくことを検討しているようですので、筑豊本線での営業運転が順調に進めば、次の導入線区を検討するとともに、勾配線区での試用などもするのではないでしょうか。
来年4月で国鉄がJRとなって30年になります。それでいながら、いまも国鉄時代に新製したディーゼルカーを多数有しているJR九州ですので、このDENCHAの性能次第では、今後、車両の更新が進む可能性がありそうです。その意味でも、注目していたい電車です。
掲載日:2016年12月02日
同じ発想の電車をJR九州が開発し、先月となる10月19日から営業運転を始めました。基本的な考え方は同じですが、JR東日本が直流1500Vで充電するのに対して、JR九州は交流20000Vで充電しています。JR東日本は首都圏を中心に直流区間が多いのに対して、JR九州は関門海峡を除いた全線が交流電化となっているためです。
また、モーターに近年普及を始めた永久磁石を使用した、永久磁石同期電動機を使用している点でも進歩しています。
車両の外観は、ご覧の通りJR九州らしいものですが、イメージカラーとして明るい青色を使っているところに特色があり、他の車両と見た目で容易に区別が付きます。
2両編成ですが、下り方の車両の床下に蓄電池を積んでいます。その部分はイメージカラーの青い覆いで覆われているので、遠目にもそれと判ります。一方、上り方の車両にはパンタグラフがあり、モーターもこちらの車両にあります。
車両形式は819系ですが、形式名はクモハBEC819-クハBEC818という、アルファベットの入った珍しいものとなりました。BECは、Battery Electric Car の略のようです。また、JR東日本の「ACCUM」と同じく愛称がつきました。「DENCHA」という愛称で、「Dual ENergy CHArge TRAIN」から名づけたということです。
隣接車両との扉近くの壁にはモニターが設置されていて、左画像のとおり、その時の電気の使用状況をリアルタイムで表示しています。この画面は、本城駅に停まるためにブレーキをかけた状態で、モーターで発生した電気を制御装置を経て蓄電池に溜めている様子を表しています。これも、JR東日本の「ACCUM」車内で見られるものと同様です。
いま、819系DENCHAが営業運転しているのは、筑豊本線の折尾~若松間10. 8kmです。筑豊地区の炭鉱が盛況だった頃に、その石炭の積み出し港として栄えた若松につながる線路だけに、非電化でありながら複線となっています。
その後の電化の進展で、鹿児島本線からの直通列車が走るようになった折尾以南は電化されたのに対して、折尾~若松間は非電化のままという支線的な扱いとなっています。その区間でJR九州初の蓄電池電車719系DENCHAの試験運転をして、さらに営業運転もはじめたという次第です。
819系DENCHAは、今のところ火曜日を除く毎日、11時過ぎから折尾~若松間を2往復し、その後車両センターのある直方までパンタグラフを上げて蓄電しながら回送で一往復します。さらに、14時過ぎからまた折尾~若松間を2往復する運用となっています。
その様子を見たところ、折尾駅停車中にパンタグラフを降ろして非電化区間での運転をはじめ、2往復を終えると折尾駅でパンタグラフを上げて、蓄電しながら直方へ向かうという対応をしていました。
車内は予想以上に静かで驚きました。VVVFインバーター制御が登場した頃は、これでもかというほど大きな音がしていたものですが、それも技術の進歩で低騒音化されているようです。
営業運転開始から1ヶ月以上経ちますが、これまでに特にトラブルの情報は無いようで、順調に走っている様子です。さらに来春には量産車6編成12両が登場して、筑豊本線で本格的な運行を開始する見込みです。筑豊本線は平坦な路線ですので、蓄電池電車の初期性能の検証には適しているのでしょう。
JR九州としてはこの先、老朽化したディーゼルカーの代替車としてDENCHAを投入していくことを検討しているようですので、筑豊本線での営業運転が順調に進めば、次の導入線区を検討するとともに、勾配線区での試用などもするのではないでしょうか。
来年4月で国鉄がJRとなって30年になります。それでいながら、いまも国鉄時代に新製したディーゼルカーを多数有しているJR九州ですので、このDENCHAの性能次第では、今後、車両の更新が進む可能性がありそうです。その意味でも、注目していたい電車です。
掲載日:2016年12月02日
●伊藤 博康(いとう ひろやす)
(有)鉄道フォーラム代表。愛知県犬山市生まれ。パソコン通信NIFTY-Serve草創期から鉄道フォーラムに関わり、1992年から運営責任者。(有)鉄道フォーラムを設立後、独自サーバでサービスを継続中。著書に「日本の “珍々”踏切」(東邦出版)「鉄道ファンのためのトレインビューホテル」「鉄道名所の事典」(東京堂出版)がある。現在、中日新聞社「達人に訊け」でもコラムを連載中。
(有)鉄道フォーラム代表。愛知県犬山市生まれ。パソコン通信NIFTY-Serve草創期から鉄道フォーラムに関わり、1992年から運営責任者。(有)鉄道フォーラムを設立後、独自サーバでサービスを継続中。著書に「日本の “珍々”踏切」(東邦出版)「鉄道ファンのためのトレインビューホテル」「鉄道名所の事典」(東京堂出版)がある。現在、中日新聞社「達人に訊け」でもコラムを連載中。